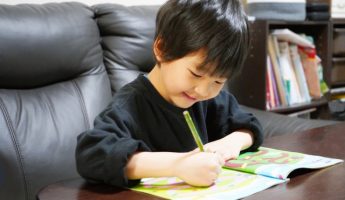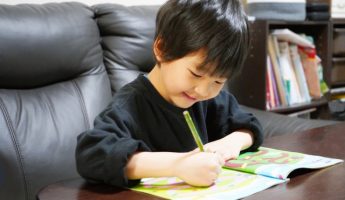
1歳でまだ話さない…それって発達障害?心配しすぎなくても大丈夫な理由

「うちの子はもうすぐ1歳になるのに、まだ一言もしゃべらない…」「1歳で発語がない=発達障害なのでは?」と不安に感じていませんか? 周りの同じくらいの月齢の子が「ママ」「ワンワン」など話し始めると、どうしても比べて心配になりますよね。実は、1~3歳頃の子どもの言葉の発達にはとても個人差があります。言葉が出るタイミングはお子さんそれぞれで、少し遅いからといってすぐに発達障害だと結論づけることはできません。
この記事では、なぜ「言葉が遅い=発達障害」とは限らないのかを発達心理学の知見から優しく説明し、言葉を育むためにご家庭でできることや専門機関の頼り方についても紹介します。お子さんの成長を温かく見守るヒントになれば幸いです。
目次
言葉の出始めには大きな個人差があります
赤ちゃんが意味のある言葉(単語)を話し始める時期には非常に幅があります。早い子は生後10ヶ月頃から初めの言葉が出ることもありますが、ゆっくりな子は1歳半を過ぎてから話し始める場合も珍しくありません。発達専門の医師によれば、遅くとも2歳までに意味のある言葉が出れば問題ないとされています。
つまり1歳でまだおしゃべりしなくても、実は「全く普通の範囲内」なのです。実際、1~3歳の時期は言葉の発達の早い・遅いがその子の個性の範囲と考えてよいほど差が大きい時期です。
たとえば、1歳代では周囲と比べて言葉が少なくても、2歳頃になってから言葉がどんどん出てくる子も多くいます。少し前まで「うちの子、全然しゃべらない…」と心配していたママ・パパが、「気づいたらおしゃべりが止まらなくなっていた!あの悩みは何だったのだろうか?」と驚くようなケースもよくあるのです。従って、今お子さんの言葉が周りよりゆっくりでも、あまり焦らなくて大丈夫です。
言葉の理解が進んでいれば心配いりません。実は、子どもは話し始める前に少しずつ言葉を「聞いて理解する力」を育んでいます。例えば1歳前後のお子さんでも、「ワンワンどこかな?」と聞くと犬のぬいぐるみを指差したり、「バイバイして」と言うと手を振ったりすることがありますよね。こうして大人の言うことが理解できているかどうかが、言葉の発達を見る上でとても重要です。
もしお子さんが意味を理解して行動できているなら、発語が多少ゆっくりでも深刻に心配する必要はないでしょう。逆に、言葉だけでなく指差しや真似っこなどコミュニケーション全般が少ない場合は、念のため一度専門機関に相談してみてもよいかもしれません(後述します)。
1歳で話さなくても発達障害とは限らない理由

言葉の発達がゆっくりだと、「発達障害(自閉症スペクトラム症など)では?」と頭をよぎることがあるかもしれません。確かに、発達障害の中には言語の遅れが初期サインとして現れる場合もあります。
しかし1~3歳の子どもは発達の個人差が非常に大きく、言葉が遅いという一点だけで障害の有無を判断することはできません。
では、発達障害の場合と言葉が遅いだけの場合、何が違うのでしょうか?
ポイントの一つは先ほど触れたように「言葉以外の部分」です。発達障害(たとえば自閉症スペクトラム症)のお子さんの場合、言葉の遅れに加えて対人コミュニケーションにも独特の特徴が見られることがあります。
例えば名前を呼んでも振り向かない、視線が合いにくい、おもちゃで遊ぶときに同じ動作の繰り返しが多い、といった様子が代表的です。
一方、言葉は出なくても表情や仕草で気持ちを伝えてくれる、こちらの指示が通っている、といった場合はお子さんなりにコミュニケーションが取れている証拠です。
言葉の遅れだけで「障害だ!」と考える必要はありません。むしろお子さんの得意なことや興味に目を向けて、「今はきっと他の成長に集中しているのかな」くらいの気持ちで見守ってあげてください。
なお、聴力の問題が言葉の遅れの原因となっているケースもあります。生後0~3歳頃までは周りの言葉を「耳から聞いて」覚えていく時期なので、もし耳の聞こえにトラブルがあるとお話しが遅れる可能性があります。普段の様子で「呼びかけにまったく反応しない」「物音に驚かない」など聴覚に不安がある場合は、早めにお医者さんに相談しましょう。耳の聞こえに問題がなければ、「この子のペースなんだな」とひとまず安心して大丈夫です。
言葉を育むためにご家庭でできること
お子さんの言葉が少ないと、「どう教えたらいいの?」と不安になると思います。まず大切なのは、焦って詰め込むのではなく楽しいやりとりの中で言葉を増やしていくことです。子どもは大好きなパパ・ママとの関わりの中でこそ、言葉をどんどん吸収していきます。おうちで今日からできる工夫をいくつかご紹介します。
- 指差しや仕草を言葉にしてあげる: お子さんが何かを指差したり、「あー!」と声を出したりしたら、すかさずそれを言葉に置き換えてみましょう。「あ、ワンワン見つけたの?そうだね、ワンワンだね!」というように、子どもの気持ちを代弁してあげるイメージです。うまく言えなくても、「そうそう、ワンワンいたね!」と笑顔で何度も繰り返してあげましょう。
- 日常の行動に言葉を添える: 着替えや食事など毎日の場面で、ぜひたくさん語りかけてみてください。例えばお出かけ前に「靴下はいてみようね。かわいい赤い靴下だね」と言ったり、おやつの時間に「はい、いちごだよ。とってもおいしいね」など、動作に合わせて簡単な言葉を聞かせます。子どもは日々の繰り返しの中で、「これが いちご っていうんだ」「赤いってこういうことか」と少しずつ言葉を理解していきます。
- テレビや動画は一緒に見てお話する: 絵本の読み聞かせや童謡などは言葉を増やすのにとても良い刺激になりますが、テレビや動画をただ見せるだけでは効果半減です。
画面に映るものを一緒に見ながら「わあ、きれいなお花だね」「今のキャラクター、面白いお顔してた!」と話しかけてみましょう。大人との会話が加わることで、メディアも立派な言葉の教材になります。 - 「聞き上手」になってゆっくり待つ: ママ・パパがお子さんにたくさん話しかけることは大事ですが、同時にお子さんの声に耳を傾ける時間も大切です。こちらが話しかけるばかりでなく、子どもが「あうー」など何か伝えようとしたときは、最後までじっくり聞いてあげましょう。
たとえ意味のある言葉でなくても、「○○だね」「○○だったのかな?」と子どもの気持ちを推し量って言葉に返すことで、「伝わった!」「もっと話したい!」という意欲につながります。
こうした関わりを続けるうちに、ある日ポロッとお子さんが新しい言葉を口にする瞬間がやって来るかもしれません。そのときは大いに褒めてあげてくださいね! パパ・ママに受け止めてもらえた安心感が、次の言葉への自信につながっていきます。
不安なときは専門家に相談してみましょう
「個人差があるのは分かっていても、やっぱり心配…」という場合は、早めに専門家に相談してみるのも一つの方法です。
1歳半健診や3歳児健診の場で相談するのはもちろん、日頃から気になることがあればかかりつけの小児科医や自治体の発達相談窓口に問い合わせてみましょう。専門家に相談すると、「この子は今こういう成長段階ですね」と客観的に見てもらえますし、必要に応じて言葉の発達を促すトレーニングや療育につなげてもらうこともできます。何より、「プロに話を聞いてもらった」というだけでもママ・パパの心がふっと軽くなることがありますよね。
公的機関だけでなく民間の発達支援サービスも充実しています。たとえば アイキューの発達支援コース(オメガコース)では、「うちの子、言葉が遅いかも…」「コミュニケーションがうまくできていないのでは?」といったお悩みについて、診断の有無に関わらず、無料体験を通して専門スタッフに相談することができます。「ちょっと様子を見てもらいたい」「どういった学習を進めれば良いのだろう」という保護者の方、悩みを一人で抱え込まず、上手に専門家の力を借りてみてください。
言葉の発達は本当に人それぞれ。「1歳でまだ話さない=発達障害」と結論づけるのは早計です。ゆっくりペースのお子さんも、愛情いっぱいに話しかけてもらいながら成長していけば、きっと自分の言葉を見つけてくれるでしょう。もちろん不安なときは周囲のサポートを借りつつ、ぜひお子さんのペースを信じてあげてください。パパ・ママの温かいまなざしが、なによりのお子さんの安心材料です。お子さんの「伝えたい!」という気持ちを大切に、これからも楽しく見守っていきましょう。
お子様の学習サポートに関しては、体験レッスンお申込みフォームよりお問い合わせください。
関連記事