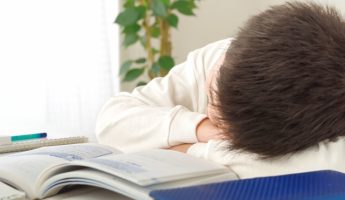「言葉がでるといいね、お話ができるといいね」 そのためには??

今回は幼少期における言葉の発達について説明をしたいと思います。
オメガコースで通われるお子様(特に乳児)の保護者様より、
「言葉が出ないけど、いつになったら出るのか?」
「言葉が出るために何か必要な取り組みはあるの?」
などなど、たくさん悩みは尽きないと思います。そのはず一緒にいる時間が誰よりも多いご家族様でしたら当然たくさんの悩みがあるのではないでしょうか?
また、
「同じ年齢の友達と比べたら、言葉数が全然少ない」
「あの子はもうお話ができるのに、うちの子どもはまだ全然お話ができない」
のように他のお子さんと比べてしまうこともあると思います。
目次
言葉の出ない子、増えない子が増えている?
2歳代の子どもをもつ母親の悩みトップ10にいつもランクインするのが、「言葉の発達」についてです。ベビーパークにいらっしゃるお母さまの心配事としても、常に上位に位置しています。実はこの20~30年の間に、2歳児で言葉が出ない子や単語の数が増えない子が非常に増えているといわれています。
子ども全体の言葉の発達が遅くなっているわけではありません。昔と同じペースで発達している子どもたちもたくさんいるのですが、言葉が出ない子の比率が年々上がってきているのです。
言葉でない子が増えている原因は、家庭環境の変化?
原因の一つとしては、家庭環境の変化にあります。昔は今に比べて近所づきあいが非常に多く、子どもたちの耳には大人たちの会話や、少し大きい子どもたちの遊ぶ声がとてもたくさん自然に入ったのです。それに比べ、現在は映像ではない自然な会話が耳に入る機会は非常に少なくなっています。親がよほど社交的でない限り、意識的かつ積極的に会話の機会を作らなければ、子どもは言葉を獲得する環境を得られにくい状況にあるのです。
しかし、2歳半で言葉が出ない子どもの発達を心配する必要はありません。「普通」「標準」という言葉の示す範囲は非常に広いからです。4歳児でも、行動の仕方、物事への興味の持ち方、他人への関わり方、そして言葉の様子などが2歳児と変わらない子どもも少なくありません。よく笑い、活発に遊び、両親のことも大好きなとてもよい子たちです。そのため、親も我が子の発達に疑問を感じることがないのが現状です。
反対に、教育に対する意識が高い家庭だと、子どもの言葉の発達を過剰に心配しすぎる傾向も見られます。クラスの友だちの言語獲得が早い場合、「うちの子は何か言葉の障害ではないか」と担任の先生に相談する方もいます。しかし、2歳半で子どもの会話がまだなかなか成立しなくても心配することはありません。標準や平均という枠の中の話なのです。現在言葉の発達が早めの家庭の場合は、子どもが成長すればするほど、高度な言語表現の獲得スピードがどんどん加速していきます。ですから、親は子どもの食事内容に気を配るのと同じくらい、言葉を育てるためのはたらきかけにも気を配ることが大切といえます。2歳の脳はまだまだ魔法のように言葉を獲得できます。心配はしすぎず安心してのびのびと育児をおこなう時こそ、教育効果は最大に発揮されます。
まずは、
ご自身のお子様の現時点でのいいところをたくさん見つけてあげて、たくさん褒めるところからやってみませんか!
きっと一番身近な存在であるお母さん、お父さんに褒められたらお子さんだって嬉しいだろうしとても気分もよくなるはず、そして笑顔がたくさん出るでしょう。人から認められることによって誰だって嬉しいし、安心することができる、この「安心する」、「安心させる環境をつくる」ということが言葉を引き出すうえで最も大切なことなのではないでしょうか。
通所当初のお子様は、特に慣れない環境下のもと、馴染のない講師とある時間を過ごすことになります。これは恐怖ですよね !!その上、一番身近な存在であるご家族ともしばらく離れなければならないこと、余計に不安がのしかかります。そのためお子様がご家族と離れる際に大泣きしてしまうこともよく見られます。(もちろん色々な性格の子がいて、物怖じしない子もいますが)
ではどうするか?
「お子さんを安心させること。」
「お子さんに笑顔になってもらうこと」
これが言葉の表出のために必要なことだと考えます。
専門的に口腔トレーニングや、発声練習を行ったからと言ってすぐに発声ができるわけではありません。お子さんに最初に笑顔になって楽しく遊べて、この環境下が安心して過ごせるということを思ってもらうことがまずは大切です。お子さんがこの環境下が安心してすごせるということがわかると自然と発声が出てくると思います。
最初は何も表出がなく、表情もあまり変化がないお子さんが楽しくすごせるようになると発声がでるようになって、喃語という言葉により近くなる発声がでて、その先に言葉の表出が出てくるのではないでしょうか。
まだ発声がおぼつかないお子さんが、楽しそうに笑顔で発声したり、喃語を表出しているのを見て「楽しそうだな、思いっきり素の自分をだしているんだな」と感じてしまいます。
だから、まずはお子さんにとって安心してすごせる環境を整えることでより発声、その先に発語が引き出されていくのでしょうか。また言葉の表出以外にも思いっきり体を動かすこと、手先の取り組みをすることで全身から刺激を与えて末端である口にエネルギーを与えていくこともとても有効な手段だと思います。
言葉を育てていく取り組みについて紹介します。
- 子どもが、今何について考えているかに気を配り、それについて語りかけます。今見ているものについて考えているとは限りません。数時間以内にあった出来事の中からもヒントを見つけるようにします。
- 大人が何か玩具や教具をもって気を引こうとすることは避けます。
- 質問はしないようにします。「質問」は子どもにとっ
- て「答えを探す」という重荷になってしまい、返事をすることを嫌いにさせがちです。
- 大人は子どもと会話をするときは、簡単な短い文を使います。
- 少しゆっくり、大きめの声で抑揚をつけて語ります。
- 言葉で伝えられていない子どもの要求を敏感に察知し、できるだけ応えてあげます。この時期それがどのくらいできるかが、後の言語発達に大きな影響を与えるとも考えられています。
- 否定的な言葉を聞かせないようにし、「声」「ことば」を聞くことは楽しいことという意識を子どもに深く刷りこみます。同じことを伝えるにしても、「何がダメなのかを教える」のではなく「どうするのがよいのかを教える」と考えて、言葉の選び方を工夫します。
- 子どもは適切な言葉が見つからない時、関係のありそうな言葉を言います。親にはおかしな表現に聞こえても、子どもにとっては決して間違えたわけではないので、子どもの言葉を否定することは避けます。
- 新しい言葉をどんどん使います。言葉が何を指し示すかがハッキリしていれば、子どもは1日に10語近く覚えられるとも言われています。
- 短時間に同じ単語をくり返し聞かせることは高い効果があります。絵本を見る時も「これはキリン。キリンの首は長い、長い。長い首のキリンさん」という感じです。
- 子どもの言葉の中に、正したい言い回しがあれば、短い文の中に取り入れて頻繁に聞かせるようにします。例えば、2歳代にはいちごもりんごも「ご!」と言う特徴があります。しかし、親は子どもの数日間の経験や今の様子から、いちごなのかりんごなのかは推測できるはずです。「ご!」と言ったら「そうだね、いちごだね」と正しい言葉と文章で返事をしてあげます。子どもに、間違いを直されていると感じさせないようにすることがポイントです。
またご家庭においても言葉の発達支援があります。声掛けであったり、絵本の読み聞かせであったり、日常生活の中でコミュニケーションの機会を増やすことも役立ちます。
●毎日の絵本の読み聞かせ
・短時間でも毎日読み聞かせをすることで、物と言葉の関連性を学べます。動物や食べ物など子どもが興味を持つテーマの絵本を選ぶと自然と語彙が増えていきます。
●興味を示した物の名前や用途を教える。
・子どもが興味を持ったものを見つけたら「これは〇〇だよ」「これでご飯を食べるんだよ」と優しく教えると言葉が身に付きやすくなります。
●歌やリズム遊びで言葉に親しむ。
・童謡や手遊び歌でリズムに触れると楽しく言葉を覚えられます。言葉とリズムの遊びが発話への良い刺激になります。
●無理に話させず楽しく会話する
・話すのを強要せず、リラックスした雰囲気で会話を楽しむことが大切です。子どもが話した時は「そうだね」「すごいね」と応じると自信と意欲が育まれます。
また各年齢(1歳~2歳)に応じた言葉の発達を促す遊びがあります。
1歳~2歳は発語の初期段階で、音や動きへの興味が高まる時期です。
この時期には、発語を引き出すための音が出るおもちゃや、親子で楽しめる仕掛けがついたおもちゃがおすすめです。
たとえば、鍵盤付きのおもちゃやボタンを押すと音が出るタイプのおもちゃは、押すたびに違う音が出る楽しさがあり、声を出すきっかけになります。
また、動物の鳴き声が再生されるおもちゃを使うことで、子どもが「ワンワン」や「モー」といった簡単な模倣を始めることが期待できます。
さらに、親が一緒に音を出しながら「これは何の音かな?」と話しかけることで、言葉と音の結びつきを自然に学べる環境をつくることができます。また1歳から2歳の子どもは、音や動きに興味を持ちやすい時期です。
この時期は、視覚や聴覚への刺激を通じて発語を促す遊びが効果的です。
たとえば、楽器のおもちゃや、音の出る絵本を使った遊びがおすすめです。親が一緒に歌を歌いながら楽器を鳴らすことで、子どもも音に合わせて声を出そうとするきっかけになります。
さらに、ボールを転がしたり、積み木を積んだりする遊びでは、動きに合わせて「転がるよ」「積んでみよう」と声をかけることで、子どもの言語理解を自然に伸ばすことができます。
この時期は「楽しさ」を大切に、親子で声を出しながら遊ぶことがポイントです。
お子様の成長は、そのお子様のスピードで成長します。
ゆっくりかもしれないけど、少しずつ着々と前進していきます。
今できること、そしてこれからの未来、ちょっとしたことでもお子様にとって大なり小なりの成長に対してしっかりと承認していくこと。
それが言葉の発達に繋がっていきます。
無料体験はこちらより
関連記事